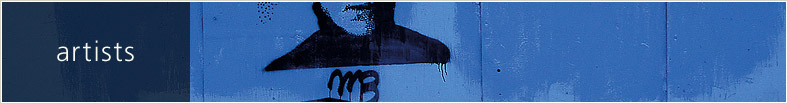鈴木徹 Tetsu SUZUKI
オフィシャルBLOG
【取り扱いギャラリー】
アートしん 銀座 黒田陶苑1964年 岐阜県多治見市に生まれる
1987年 龍谷大学文学部史学科卒業
1988年 京都府陶工職業訓練校成形科卒業
1991年 第38回日本伝統工芸展入選 以降15回入選
1993年 銀座黒田陶苑 二人展
1994年 第25回東海伝統工芸展入選 以降毎年入選
1995年 銀座黒田陶苑 二人展
1997年 第44回日本伝統工芸展 入選 日本工芸会正会員になる
銀座黒田陶苑にて個展
1999年 第30回東海伝統工芸展 「岐阜県教育委員会賞」 受賞
銀座黒田陶苑にて個展
2001年 第32回東海伝統工芸展 「東海伝統工芸展賞」 受賞
2002年 日本橋三越本店画廊にて個展
2003年 第34回東海伝統工芸展 「東海伝統工芸展賞」 受賞
第17回日本陶芸展 入選
第50回日本伝統工芸展 「新人賞」 受賞
〈受賞作「緑釉鉢」が兵庫県陶芸美術館に収蔵される〉
名古屋松坂屋本店画廊にて個展
2004年 名古屋芸術大学美術学部非常勤講師就任
高松天満屋画廊にて個展
2005年 第1回菊池ビエンナーレ 「大賞」 受賞
〈受賞作「緑釉鉢」が菊池寛実記念 智美術館に収蔵される〉
第18回日本陶芸展 入選 (賞候補)
第36回東海伝統工芸展 審査員 招待出品
日本橋三越本店画廊にて個展
美濃陶磁展(多治見産業文化センター)出展
NHKBS-1 「器夢工房」 に出演 『淡く濃く緑映えて』
2006年 銀座黒田陶苑にて個展
安達学園 第1回安達賞 正賞「緑釉長皿」制作
京都 伝統未来塾公開シンポジウム「茶陶の昨日・今日・明日」パネラーとして出席
岐阜高島屋画廊にて個展
多治見市文化工房ギャラリーヴォイス 「やきものの現在」 展 出展
2007年 第38回東海伝統工芸展 「東海伝統工芸展賞」 受賞
東美アートフェア(東京美術倶楽部) 「緑の形象 鈴木徹展」
フジテレビ番組 「今宵ひと皿」 に 『緑釉鉢』 が取り上げられる
NHKBS-1 「器夢工房」 総集編 『作る楽しさ使う楽しさ』 に出演
名古屋松坂屋本店画廊にて個展
2008年 愛知県陶磁資料館企画展 「東海現代陶芸の今」 展 出展
第39回東海伝統工芸展 審査員 招待出品
長江洞画廊 「鈴木徹・若尾経 二人展」
第36回新作陶芸展 「日本工芸会賞」 受賞
丸栄美術画廊「伊藤渡・鈴木徹 二人展」
日本橋三越本店画廊にて個展
加藤洋二 Yoji KATO
【取り扱いギャラリー】
アートしん1953 岐阜県土岐市生まれ、加藤卓男に師事
1979 日展入選
1982 朝日陶芸展 朝日陶芸賞
1986 日本新工芸展 外務省買い上げ
彫刻の森、明日をひらく新工芸展 奨励賞
1987 中日国際陶芸展 名古屋市長賞
八木一夫大賞展 ('89)
朝日クラフト展 ('89)
1988 オ-ストラリア200年祭記念陶芸展
1990 オ-ストラリア朝日陶芸展
1991 焼き〆大賞展 記念賞
東海の作家たち 愛知県芸術文化センタ-
1992 国際陶磁器フェスティバル美濃'92
審査員特別賞
岐阜県陶磁資料館 永年保存
1993 第12回日本陶芸展
テ-ブルウェアフェスティバル、優良賞('94)
野外制作93 信楽陶芸の森
新世代の陶芸展 愛知陶磁資料館
1994 丹南ア-トフェスティバル
1995 現代茶陶展 織部大賞
金沢工芸大賞展 金沢工芸大賞
現代の陶彫-日本と西洋
1996 美濃陶芸協会 幸兵衛賞
茶道美術公募展
草月花の器展
1997 ユ-モア陶彫展 奨励賞
1999 美濃陶芸協会 庄六賞
2004 イギリス グラスゴ-美術大学
マッキントッシュギャラリ-
MINOセラミックスNOW2004
岐阜県現代陶芸美術館
2005 現代茶陶展 銀賞
岐阜県芸術文化奨励賞
2008 加藤洋二個展 (日本橋高島屋/東京)
加藤陽児 Yoji KATO
【取り扱いギャラリー】
アートしん1958年 生まれ
兼宗窯(けんそうがま)
多治見工業高校窯業専攻科卒業
1992年 「聖地」で美濃陶芸大賞を受賞。東濃信用金庫の永年保存作品
1999年 加藤陽児陶芸展 (松坂屋本店/名古屋)
2005年 「青風」で美濃陶芸大賞を受賞
2006年 加藤陽児作陶展 (松坂屋本店/名古屋)
加藤康景 Yasukage KATO
【取り扱いギャラリー】
アートしん 銀座 黒田陶苑1964年 岐阜県土岐市に生まれる。父は美濃陶祖家13代加藤景清(清三)
1982年 岡山県備前市、人間国宝山本陶秀に師事
1987年 名古屋芸術大学彫刻科卒業
1989年 岐阜県美術展受賞
1992年 美濃陶芸協会会員
1993年 東海伝統工芸入選
1999年 美濃陶芸大賞受賞
2000年 美濃陶芸大賞作品永年保存(岐阜県陶磁器資料館)
2001年 美濃陶祖14代継承 雅号加藤康景と命名
2003年 美濃陶芸庄六賞茶碗展庄六賞受賞
主な展覧会
1988年 加藤康景個展 (しぶや黒田陶苑/東京)
1990年 加藤康景個展 (しぶや黒田陶苑/東京)
1991年 加藤康景個展 (日本橋高島屋/東京)
1993年 加藤康景個展 (大丸/京都)
1994年 加藤康景個展 (高島屋/横浜)
1995年 加藤康景個展 (日本橋高島屋/東京)
1996年 加藤康景個展 (なんば高島屋/大阪)
加藤康景個展 (大丸/京都)
1997年 加藤康景個展 (日本橋高島屋/東京)
1998年 加藤康景個展 (銀座黒田陶苑/東京)
加藤康景個展 (高島屋/横浜)
加藤康景個展 (なんば高島屋/大阪)
1999年 加藤康景個展 (日本橋高島屋/東京)
2002年 加藤康景作陶展 (松坂屋本店/名古屋)
加藤康景個展 (銀座黒田陶苑/東京)以降02年)
2003年 ニューヨークアジアンアートフェアーにて個展
加藤康景個展 (日本橋高島屋/東京)
飯田眞人(飯田真人) Masato IIDA
【取り扱いギャラリー】
アートしん1949年 長崎県生まれ
1972年 京都今橋製陶所(貴古窯)に入所
1974年 京都府立陶工訓練校成形科修了後北村和善窯に入所
この時期「釉薬研究会」に参加
陶磁器釉薬の研究誌「高火度釉基礎試験」を共同発行
1976年 岐阜県多治見市に移転
1977年 多治見工業高校窯業専攻科修了
多治見市市之倉町にて独立「真陶房」を開窯。以後、青瓷の器を中心に制作
1985年 この年より東京、大阪、名古屋、岐阜ほか各地で個展を開催
1990年 土岐市五斗蒔に移転。工房の名称を「天青窯」に変更
1999年 飯田眞人・陽子作陶展 (丸栄工芸サロン)
2001年 飯田眞人・陽子作品展 (丸栄美術サロン)
2006年 松坂屋本店にて個展開催
2008年 松坂屋本店にて「飯田眞人陶芸展」を 開催
日本伝統工芸展、東海伝統工芸展(1985年愛知県知事賞受賞)、中日国際陶芸展、Bonsai の器展に入選
安藤工 Takumi ANDO
【取り扱いギャラリー】
アートしん現在の仙太郎窯の4代目として岐阜県多治見市市之倉町に生まれる。父は安藤日出武(岐阜県重要無形文化財)
多治見工業高校
2002年 「灰釉(はいゆう)彩文器」が美濃陶芸作品永年保存に指定
2004年 美濃陶芸展 「彩文の器」が美濃陶芸大賞を受賞
展覧会
2002年 安藤工作陶展 (日本橋三越/東京)
2003年 安藤工陶芸展 (松坂屋本店/名古屋)
2006年 安藤工陶芸展 (松坂屋本店/名古屋)
2007年 安藤工・前田和伸 (瀬戸市新世紀工芸館)
加藤孝造 Kozo KATO
【取り扱いギャラリー】
アートしん1935年 3月12日、岐阜県端浪市に生まれる
1953年 光風会展(洋画)に初入選、以後8回出品
岐阜県陶磁器試験場にて加藤幸兵衛氏に陶芸の指導を受ける
1954年 第10回日展(洋画)に初入選
1955年 岐阜県陶磁器試験場工芸科(主任技師)のころより進路を陶芸に固める
1959年 朝日新聞社主催 現代日本陶芸展に初入選
加藤孝造個展(初個展) (ボニエル工芸店/ニューヨーク)
1962年 朝日新聞社主催 現代日本陶芸展課題作の部にて三席に入賞
日本伝統工芸展に「志野日帯文壷」初出品初入選(以後同展に出品)
1963年 朝日陶芸展入選入賞 以後受賞を重ねる
1965年 多治見市星ケ台に薪・石炭併用の倒焔式単室窯を築く
1966年 日本工芸会正会員に就任。
1967年 朝日陶芸展で「鉄釉壺」が優秀賞を受賞。同展評議員となる
1968年 「鉄釉花器」で第15回日本伝統工芸展朝日賞を受賞
1969年 第1回東海伝統工芸展最高賞(第一席)を受賞
1970年 岐阜県陶磁器試験場工芸科を退職し、多治見市星ケ丘で制作活動に入る
陶房に来訪した荒川豊蔵氏の助言を得て穴窯築窯を築く
多治見市星ケ丘に半地下式単室穴窯を築く
日本陶芸展(毎日新聞社主催)に推薦招待出品となる(以後隔年)
朝日陶芸展審査員となる
1972年 可児市久々利平柴谷に穴窯と登窯2基を築き、桃山の陶芸技術の追求に努める
1975年 中日国際陶芸展評議員となる。以後主として個展を作品発表の場とする
1981年 「日華現代陶芸展」(中華民国歴史博物館主催)に招待出品
1982年 「現代の茶陶百碗展」(読売新聞社主催)招待出品
1983年 全日本伝統工芸選抜展招待出品
加藤幸兵衛賞が創設され第一回「加藤幸兵衛賞」を受賞
東海伝統工芸展鑑査員となる
日本工芸会東海支部幹事となる(陶芸部会長)
「伝統工芸30年の歩み展」(東京国立近代美術館主催)出品
1984年 中日国際陶芸展審査員となる
1985年 日本陶磁協会賞受賞。
岐阜日々新聞社賞「教育文化賞」を受賞
1986年 中日国際陶芸展審査員となる
1990年 美濃陶芸協会会長となる
岐阜県文化懇話会員就任
1991年 現代陶芸の美展(セゾン美術館)招待出品
多治見市無形文化財(志野・瀬戸黒)認定保持者となる
1994年 東海テレビ文化賞受賞
1995年 岐阜県指定重要無形文化財(志野・瀬戸黒)認定保持者となる
1996年 現代日本陶芸の秀作―アジア巡回展出品
1997年 (社)美濃陶芸協会名誉会長となる
1998年 中日文化賞を受賞
岐阜県芸術文化顕彰受賞
1999年 陶房に古民家を移築「風塾」を創設
2002年 日本陶芸展(毎日新聞社改組)招待(以後隔年)
国際陶磁器フェスティバル・美濃(陶芸部門)審査員
2003年 第4回織部賞受賞
日本伝統工芸展50周年記念「技の美」展出品
岐阜県文化財保護審議会委員
岐阜県現代陶芸美術館協議会会長
2005年 岐阜県陶磁資料館顧問
地域文化功労者文部科学大臣表彰
板谷波山 Hazan ITAYA
1872年 茨城県真壁郡下館町(現・筑西市)に醤油醸造業者の息子として生まれる。本名は板谷嘉七
1889年 東京美術学校(現・東京芸術大学)彫刻科に入学。岡倉天心、高村光雲らに学ぶ
1894年 東京美術学校卒業
1896年 石川県工業学校木彫科主任教諭として金沢に赴任する
1898年 石川県工業学校の木彫科が廃止され陶磁科を担当、陶芸を本格的に研究する
1903年 石川県工業学校を辞職し、東京高等工業学校窯業科嘱託となる
東京府北豊北(東京都北区)に住居と工房を建てる
郷里の筑波山に因んで「波山」と号す
1906年 日本美術協会展に3点出品、技芸褒状一等を受章
うち1点を益田鈍翁に買上げられる
1908年 「日本美術協会展」に出品、銅賞牌を受賞
1909年 日本美術協会展の委員となる。この折、皇后陛下に作品を献上
1911年 東京勧業博覧会陶磁七宝部の委員となる
全国窯業品共進会にて一等賞金牌を受賞
1914年 大正天皇即位記念東京大正博覧会の監査員となる
同会にて「葆光彩磁孔雀唐草文大花瓶」が金牌を得、宮内省が買上げる
1917年 第57回日本美術協会展に「珍果文花瓶」を出品、1等賞金牌を受賞(同展最高の賞)
1918年 新潟県長岡市で「波山会」が作られる
この頃より「彩壺会」の講演会に参加
1927年 帝展審査委員となる。工芸家団体茨城工芸会結成し、会長就任
1929年 工芸家として初の帝国美術院会員となる。帝展の工芸部主任審査員となる
1930年 パリでの日本美術展覧会に尽力した功績により、フランス大統領よりアカデミー勲章を贈られる
1933年 郷里の高齢者に鳩杖を制作して寄贈する(1952年まで作り続け、総数319点に及ぶ)
1934年 帝室技芸員となる
1937年 帝国芸術院会員となる
1938年 郷里の日中戦争戦没者遺族に、観音像や香炉を制作寄贈して霊を慰める
(1956年まで作り続け、総数281点に及ぶ)
1953年 陶芸家として、初の文化勲章受章
1954年 横山大観とともに茨城県名誉県民に推挙される
1960年 重要無形文化財(萩焼)保持者として認定されるが辞退する
1963年 「財団法人波山記念会」設立。直腸癌のため91歳で死去
2002年 「珍果文花瓶」が、重要文化財に指定
(※同年に指定された宮川香山の作品とともに、明治以降の陶磁器としては初の重要文化財指定。また、茨城県筑西市にある波山の生家は茨城県指定文化財として保存公開されている)
若尾利貞 Toshisada WAKAO
【取り扱いギャラリー】
アートしん1933年 岐阜県多治見市に生まれる
1960年 中部美術展入選、ニュークラフト賞受賞
1961年 岐阜県総合デザイン展受賞
1963年 朝日陶芸展初入選
1965年 日本伝統工芸展初入選
1968年 初個展開催
1970年 日本工芸会正会員
1971年 日本陶芸展入選、海外選抜展出品
1972年 美濃新人賞受賞
1973年 中国国際陶芸展入選
1986年 加藤幸兵衛賞受賞
ロンドン・ロイヤルアルバートミュージアム買い上げ永久保存
1989年 ロンドン・ロイヤルアルバートミュージアム買い上げ永久保存
日本陶磁器協会賞受賞
1990年 岐阜新聞大賞受賞
1995年 多治見市無形文化財技術保持者に指定
2003年 岐阜県重要無形文化財保持者に認定
2004年 東京国立近代美術館 作品買い上げ
展覧会
1968年 若尾利貞個展(初個展) (名鉄百貨店/名古屋)
1970年 若尾利貞個展 (名鉄百貨店/名古屋)
1972年 若尾利貞個展 (名鉄百貨店/名古屋)
1975年 若尾利貞個展 (高島屋・東京)
1976年 若尾利貞個展 (NKデパート/スウェーデン・ストックホルム)
若尾利貞個展 (松坂屋/名古屋)
1977年 若尾利貞個展 (高島屋/東京)
1978年 若尾利貞個展 (高島屋/大阪)
若尾利貞個展 (松坂屋/名古屋)
1979年 若尾利貞個展 (高島屋/東京)
1980年 若尾利貞個展 (高島屋/大阪)
若尾利貞個展 (松坂屋/名古屋)
1981年 若尾利貞個展 (高島屋/東京)
若尾利貞個展 (高島屋/米子)
1982年 若尾利貞個展 (高島屋/大阪)
1983年 若尾利貞個展 (松坂屋/名古屋)
若尾利貞個展 (壺々現)
1984年 若尾利貞個展 (高島屋/大阪)
若尾利貞個展 (天満屋/広島)
1985年 若尾利貞個展 (トキハデパート/大分)
若尾利貞個展 (高島屋/東京)
1986年 ワシントン・スミソニアン博物館出品
若尾利貞個展 (大沼デパート/山形)
若尾利貞個展 (鶴屋デパート/熊本)
若尾利貞個展 (高島屋/大阪)
1987年 若尾利貞個展 (高島屋/岐阜)
若尾利貞個展 (大丸/下関)
若尾利貞個展 (松坂屋)
若尾利貞個展 (寛土里)
1988年 高島屋創立80周年記念展 東京店、大阪店
1989年 若尾利貞個展 (高島屋/大阪)
1991年 若尾利貞個展 (高島屋/京都・岡山・東京)
「陶」出版
1992年 若尾利貞個展 (高島屋/大宮)
1993年 若尾利貞個展 (高島屋/大阪)
1994年 若尾利貞個展 (高島屋/岐阜)
1995年 若尾利貞個展 (高島屋/京都)
1996年 若尾利貞個展 (高島屋/大阪)
1997年 一宮市環境センターにて陶壁―群鶴―制作
若尾利貞個展 (高島屋/高崎)
2000年 若尾利貞個展 (高島屋/大阪)
2001年 若尾利貞個展 (松坂屋)
2003年 若尾利貞個展 (ダイイチギャラリー/ニューヨーク)
若尾利貞個展 (高島屋/岐阜・大阪・米子)
2004年 若尾利貞個展 (高島屋/東京)
2005年 若尾 利貞・経 親子作陶展 (近鉄四日市店/四日市)
2006年 若尾利貞個展 (高島屋/京都)
2008年 若尾利貞個展 (高島屋/大阪・岡山・米子)
若尾経 Kei WAKAO
【取り扱いギャラリー】
アートしん1967年 岐阜県多治見市に生まれる。父は若尾利貞
1993年 日本大学芸術学部写真学科卒業
1995年 多治見氏陶磁器意匠研究所修了
1997年 日本陶芸展 入選
朝日陶芸展 秀作賞
出石磁器トリエンナーレ 入選
1998年 国際陶磁器フェスティバル美濃 銅賞
金沢わん・One大賞 招待出品
1999年 信楽陶芸の森 陶芸の20世紀展 招待
2005年 若尾利貞・経親子作陶展 (近鉄四日市店/四日市)
2006年 若尾経展 (伊藤美術店/名古屋)
2007年 若尾経陶芸展 (松坂屋本店/名古屋)
2008年 若尾経作陶展 (日本橋三越本店/東京)
鈴木蔵(鈴木藏) Osamu SUZUKI
【取り扱いギャラリー】
アートしん 銀座 黒田陶苑1934年 岐阜県土岐市駄知町に生まれる
1953年 岐阜県立多治見工業高校窯業科を卒業
丸幸陶苑試験室に入社
1959年 第8回現代日本陶芸展(朝日新聞社主催)に「志野丸皿」を初出品し佳作
第6回日本伝統工芸展に初出品し入選
1961年 第10回現代日本陶芸展第一席
第8回日本伝統工芸展NHK会長賞受賞
1962年 チェコ国際陶芸展グランプリ受賞
1967年 第10回日本伝統工芸展日本工芸会会長賞受賞
1969年 日本陶磁協会賞受賞
1972年 第19回日本伝統工芸展監査員
1975年 第22回日本伝統工芸展特待者認定
1982年 第19回日本陶磁協会金賞受賞
1987年 芸術選奨文部大臣賞受賞
中日文化賞受賞
岐阜新聞文化賞受賞
岐阜県芸術文化顕彰受賞
1992年 藤原啓記念賞受賞
東海テレビ文化賞受賞
1994年 重要無形文化財「志野」保持者認定(人間国宝)
1995年 紫綬褒章授章
1998年 鈴木蔵個展 (パリ三越エトワール/パリ)
1999年 パリ展帰国記念 鈴木蔵個展 (日本橋三越/東京、名古屋三越)
2001年 志埜 人間国宝 鈴木蔵展 (難波高島屋/大阪)
2008年 鈴木蔵展 (日本橋三越/東京)
加藤高宏 Takahiro KATO
【取り扱いギャラリー】
アートしん1972年 愛知県名古屋市生まれ。父は加藤重高、祖父は加藤唐九郎
1990年 名古屋芸術大学洋画科入学
1994年 中国の西安、敦煌を経てウルムチより、カザフスタン、ウズベキスタン、ロシア、東欧、西欧諸国を陸路でまわり、スペインのグラナダに約一年間滞在し、語学、美術を学ぶ。
帰国後、重高工房にて作陶。
1997年 加藤唐九郎・重高・高宏三人展 (大和/金沢)
加藤重高・高宏 父子展 (丸栄/名古屋)
1998年 加藤重高、高宏父子展 (そごう/広島)
1999年 「一碗のいのり」加藤高宏展 (阪急梅田本店/大阪)
2000年 加藤高宏展 (丸栄/名古屋)
加藤唐九郎・重高・高宏三人展 (天満屋/岡山)
2001年 加藤高宏展 (日本橋三越本店/東京)
2002年 加藤高宏展 (画廊文錦堂/岐阜)
加藤高宏展 (阪急梅田本店/大阪)
2003年 加藤高宏展 (香林坊大和/金沢)
2004年 加藤高宏展 (画廊文錦堂/岐阜)
加藤高宏展 (日本橋三越本店/東京)
2005年 加藤高宏展 (阪急梅田本店/大阪)
「うつわ」の芸術性を問う 加藤高宏の試み (常滑 アート&デザイン・リン)
2006年 加藤高宏展-志野・瀬戸黒・黄瀬戸- (しぶや黒田陶苑/東京・渋谷)
加藤高宏展 (丸栄/名古屋)
2007年 加藤唐九郎・重高・高宏展 (近鉄四日市店/四日市)
加藤高宏展 (日本橋三越本店/東京)
森北伸 Shin MORIKITA
1969 愛知県名古屋市生まれ
1992 愛知県立芸術大学美術学部彫刻科卒業
現在 愛知県立芸術大学美術学部彫刻科准教授
2008 第14回 石田財団芸術奨励賞受賞
個展
1992 個展(NAF、名古屋)
1993 個展(ウエストベス ギャラリー、名古屋、愛知)
1994 個展(ウエストベス ギャラリー、名古屋、愛知)
1998 "Can't touch house and home"(白土舎、名古屋、愛知)
2000 窓の向こうはすべてウソ(長久手町文化の家、愛知)
recent works (白土舎、名古屋、愛知)
2002 in the room (Mixed Media、静岡)
2003 坂の途中の家 (白土舎、名古屋、愛知)
2004 a colony(白土舎、名古屋、愛知)
2005 6 by 9 (白土舎、名古屋、愛知)
2006 Raw Life(白土舎、名古屋、愛知)
2007 Nowhere man (白土舎、名古屋、愛知)
グループ展
1994 Young of Youth (ウエストベス ギャラリー、名古屋、愛知)
となりのけはい (愛知芸術文化センターアートスペースX、名古屋、愛知)
1995 2人展(杉戸洋)(ケンジ タキギャラリー、名古屋、愛知)
1996 小品展 (ギャラリーTAF、京都)
1997 House(三人展)(アートスペースX、名古屋、愛知)
1998 Innocent Minds (愛知芸術文化センター、名古屋、愛知)
House(二人展)(アートスペースX、名古屋、愛知)
2001 現代美術2001 NAGOYA(名古屋市民ギャラリー矢田、名古屋、愛知)
2003 現代美術のポジション 2003(名古屋市美術館、名古屋、愛知)
2004 人間をつくってください(名古屋市民ギャラリー矢田、名古屋、愛知)
2005 ベリー ベリー ヒューマン(豊田市美術館、豊田、愛知)
2006 画家の立体と彫刻家の平面 (白土舎、名古屋、愛知)
愉しき家(愛知県美術館、名古屋、愛知)
2007 city_net Asia 2007(ソウル市美術館、ソウル、韓国)
2008 石田財団芸術奨励賞受賞記念展(電気文化会館、名古屋、愛知)
加藤重高 Shigetaka KATO
【取り扱いギャラリー】
アートしん1927年 4月26日愛知県瀬戸市に生まれる。父は加藤唐九郎、岡部嶺男は長兄
1945年 愛知県瀬戸窯業学校卒業後、父唐九郎のもとで作陶生活に入る
1959年 日展出品(以後毎年1971まで)
1966年 日展特選北斗賞を受賞
1967年 日本陶磁協会賞を受賞
1969年 父唐九郎と中近東、ヨーロッパを視察旅行
1970年 日本現代工芸展工芸賞を受賞
1971年 この年以降、作品発表を主に個展とし、東京・名古屋・大阪・九州・北海道と全国各地で個展開催
1973年 父唐九郎と北京、唐山、景徳鎮、石湾など視察旅行
1978年 北京、上海、長沙、広州を視察旅行
1980年 バンチェン、スワンカロク、スコタイを視察旅行
1981年 故宮博物院(台湾)、中国敦煌を視察旅行
1983年 中南米を視察旅行(マヤ、インカ土器研究)
1990年 「加藤重高作品集」講談社より出版
1997年 「土よ炎よ」風媒社より出版
1998年 名古屋芸術家特賞を受賞
2003年 英文の「現代日本工芸の巨匠」というシリーズの中に載る
日本現代工芸展現代工芸賞
朝日陶芸知事賞ほか
鯉江良二 Ryoji KOIE
【取り扱いギャラリー】
銀座 黒田陶苑1938 愛知県常滑市に生まれる
1957 常滑高校窯業科卒業
日本タイルブロック社入社
1962 常滑市立陶芸研究所入所
現代日本陶芸展入賞
1966 独立
1967 朝日陶芸展入選入賞
1971 「土に帰る」発表
1989 愛知県立芸術大学助教授就任
1990 「チェルノブイリ・シリーズ」発表
1992 日本陶磁協会賞受賞
愛知県立芸術大学美術学部陶芸科教授に就任(〜2004.3)
1994 岐阜県恵那郡上矢作町へ工房を移転
2001 織部賞受賞
2002 常滑市奥条天竺に穴窯を築窯
2003 愛知県立芸術大学 退官
2005 中日文化賞受賞
2008 日本陶磁器協会賞・金賞受賞
主な個展
1990 鯉江良二個展 (山木美術/大阪)
1993 鯉江良二個展 (ギャラリー顕美子/愛知・刈谷)
1996 鯉江良二個展 (岐阜県立美術館)
1997 鯉江良二個展 (土画廊/ソウル)
1998 鯉江良二個展 (ギャラリーベッソン/英国・ロンドン)
鯉江良二個展 (ギャラリー顕美子/名古屋)
鯉江良二個展「新作ガラスと陶展」 (山木美術/大阪)
1999 鯉江良二個展「壷展」 (高島屋/大阪、東京、横浜、岡山巡回)
やきもの新感覚シリーズ5 COSMIC クレイワーク(個展)(INAX世界のタイル博物館)
2000 鯉江良二個展(ブライアン・オーノ・ギャラリー/アメリカ・シアトル)
鯉江良二個展「Made in SEATTLE」 (山木美術/大阪、名鉄百貨店/名古屋)
2001 鯉江良二個展「オリベ」 (山木美術/大阪)
鯉江良二個展「織部賞受賞記念展」 (山木美術/大阪)
2003 退官記念展(愛知県立芸術大学/愛知・長久手)
2004 鯉江良二個展「赤絵展」 (山木美術/大阪)
鯉江良二陶展 メイド・イン・ニュージャージー (名鉄百貨店/名古屋)
鯉江良二個展「出版記念展 Made In New Jersey」 (山木美術/大阪)
2005 鯉江良二個展(ブートウェル・ドレイパー・ギャラリー/オーストラリア)
2006 鯉江良二個展(ブートウェル・ドレイパー・ギャラリー/オーストラリア)
Stealing God's Fire RYOJI KOIE(亜洲美術館/韓国・大田)
2007 鯉江良二個展「伝統と実験」 (兵庫陶芸美術館/兵庫)
2008 「思う壷」鯉江良二展 (パラミタミュージアム/三重)
鯉江良二展 (銀座 黒田陶苑/東京・銀座)
主なグループ展、ワークショップほか
1970 6人の日本青年陶芸家展(スクリプス大学/アメリカ)
1972 第3 回バロリス国際陶芸ビエンナーレ展 国際名誉大賞受賞
第30回「ファエンツァ国際陶芸展」出品 (ファエンツァ、イタリア)
1977 「現代美術の鳥瞰展」出品 (京都国立近代美術館)
1982 「今『土と火で何が可能か』展」出品 (山口県美術館)
1986 「今日の造形『土と炎』展」出品 (岐阜県立美術館)
「日本の前衛 1910−1970」出品 (パリ ポンピドーセンター)
1987 「60 年代の工芸」出品 (東京国立近代美術館・工芸館)
「現代のイコン」出品 (埼玉県立近代美術館)
1988 「近代日本の陶芸」出品 (福島県立美術館)
1989 「ユーロバリア89ジャパン現代陶芸展」(モンス市立美術館/ベルギー)
1990 「現代の土」出品 (東京都美術館)
1992 ウエストミシガン大学にてワークショップ(アメリカ ミシガン州 カラマズ)
1993 「現代の陶芸 1950∼1990 展」出品 (愛知県美術館)
1993-94 「日本を代表するスリーアーチスト展」 (アメリカ、日本巡回)
1994 名古屋発現代美術展(名古屋市美術館、名古屋)
1994 「国際現代陶芸展―今日のうつわと造形」出品 (愛知県陶磁資料館)
1995 「戦後文化の軌跡1945-1955」(広島市現代美術館、他4ヶ所巡回)
1996 韓・日陶芸交流展 李 基柱+鯉江良二 二人展(KBSギャラリー/韓国・釜山)
「今日の日本美術展Ⅱ」出品 (タマヨ美術館/メキシコ)
「INTER・ACTION」 (ケンジタキギャラリー/名古屋)
1997 「ソウル セラミック アート ビエンナーレ 1997」 (ソウル市立美術館/韓国)
1998 「Art on Element--水と火と風と地と」 (北海道立釧路芸術館、北海道)
1999 第6回韓日陶芸大学企画・参加(恵那、岐阜)
「20世紀世紀末の陶芸展」(コルドバ、スペイン)
ワークショップ(益子、栃木)
2000 ワークショップ(かわら美術館、高浜、愛知)
ワークショップ(札幌芸術の森、北海道)
ワークショップ(江別セラミックセンター、北海道)
韓国国際薪窯フェスティバル:ワークショップ(ソウル、韓国)
ワークショップ(北アリゾナ大学、アメリカ)
驪州国際陶磁器ワークショップ(ソウル、韓国)
2001 ワークショップ(キーウェスト、フロリダ、アメリカ)
「現代茨城の精鋭たち」(茨城県陶芸美術館/茨城・笠間)
野焼きワークショップ(愛知県陶磁資料館、愛知)
ワークショップ(ピーター・カラス工房、ニュージャージー、アメリカ)
「第1回京畿道世界陶磁ビエンナーレ」(韓国/利川)
BANBANワークショップ(滋賀県社会福祉事業団、滋賀)
2002 野焼きワークショップ(高知県立美術館、高知)
アルミのモニュメント制作(厚田村、北海道)
2003 ワークショップ(かわら美術館、高浜、愛知)
「大地の芸術―クレイワーク新世紀―」出品 (大阪国立国際美術館)
「織部―転換期の日本美術」出品 (メトロポリタン美術館/ニューヨーク)
2004 ワークショップ:景徳鎮陶芸会議(中国)
ワークショップ:The Naked Truth(アイオワ州、アメリカ)
「MINO CERAMICS NOW 2004」(岐阜県現代美術館/岐阜)
2005 「日仏現代陶芸交流展2005 IN 笠間 記念展」 (ギャラリー顕美子/愛知・名古屋)
2007 「第4回京畿道世界陶磁ビエンナーレ」(利川、韓国)
TAMBA STYLE−伝統と実験− 鯉江良二 IN TAMBA
2008 交差する視点とかたち vol.2--ワークショップ、レクチャー(札幌芸術の森、北海道)
日本陶磁協会賞・金賞受賞記念 三原研・鯉江良二展(和光並木ホール/東京)
ヒロシマ賞記念トロフィー制作