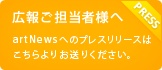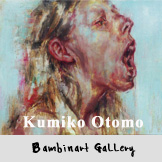"影に吠える" 秋山幸 伊藤雅恵 問谷明希 村岡佐知子 Ai Kowada Gallery
2012年6月16日(土)~7月14日(土)
展覧会開催時の 火曜日から土曜日 / 12:00-19:00 日、月、祝日 休廊
Ai Kowada Gallery

影に吠える4つの方法論
堀 元彰
一見したところその作風も方法論も異なる4人のアーティストの絵画展。
「影に吠える」という展覧会名は4人で話し合って決めたものだというが、じつに深みのある、
気の利いた命名だ。
異国に旅立つ恋人の影の輪郭をなぞったことを絵画芸術の起源として挙げる、プリニウスの
『博物誌』を引き合いに出すまでもないだろう。美術史的に見ても、影は、絵画における
再現性や実在性の追求にとって不可欠なものだったし、光とともに絵画表現にとって
きわめて重要な要素の一つでありつづけてきたからだ。
秋山幸の絵画には、中国やペルシアのそれを想起させる文様が描かれている。
本来平板なはずの文様は、部分的に陰影や濃淡を施され、複雑な階層をなす。秋山はさらに
それらの階層を巧みに重ね合わせることで、平面的かつ装飾的でありながら、
豊かな奥行をもつ魅惑的な絵画空間を作り上げている。
伊藤雅恵の作品は、会場のなかで最も鮮烈なその色彩にまず目を奪われる。
画面の中心には、両手両足を大きく広げて闊歩し、あるいは遊泳する女性像が描かれている。
鮮やかな色彩が乱反射する眩い画面のなか、赤や白の単一色で描かれた人物はまるで
影絵のようだが、不思議な実体をもって立ち現われている。
問谷明希は、自ら撮影した写真を切り貼りしたコラージュを参考にカンヴァスに向かう。
彼女の制作方法がユニークなのは、制作途中のカンヴァスを再び写真でコラージュして、
画面の再構成や微修正を試みる点だ。それはまるで実体と影の間を自由に行き来しながら、
普遍的な真実の表現に迫ろうとするかのようだ。
フェンスや暗闇ごしに垣間見える風景を視覚化した村岡佐知子の作品は、抑制の効いた、
味わい深い色彩がじつに印象的だ。彼女の作品では、視界をさえぎるものこそが目に見える事物を
より顕在化させ、その存在を際立たせ、あるいは、広大な時空間へと見る者の想像力を掻き立てる。
4人のアーティストのアプローチはさまざまだが、その臆することのない、果敢な営為
が微妙に交錯し合いながら、それぞれが追求する絵画のありようを浮かび上がらせてい
た。(東京オペラシティ アートギャラリー チーフ・キュレーター)
自分の視野や心象風景は、他者と完全には共有できない。
わたしたちはこの当たり前の境界を、無意識に了解して日々を過ごしている。
例えば昨日見た夕焼けの美しさを人に伝えようとする時、物理的に視界を
切り取る写真にも、想像力を引き出す文章にも限界があるだろう。
絵を描くこともまた、その境界に挑む行為なのだと4人の絵を前にして改めて思う。
伊藤雅恵はこれまでの抽象性をひそめ、自身や近しい友人をモデルに、
何かに追われているような鬼気迫る形相や、大地を踏みしめ颯爽と歩く凛とした
女の子が見せる、生命力溢れる一瞬のきらめきを、ほとばしるような
筆致と極色彩で画面にとどめた。
訪れた北欧の風景を描いた問谷明希は、画面に様々な質感をもたらすため、
自ら現地で撮影してきた写真プリントを用いたコラージュを下絵に、
自らが包まれたやわらかな北欧の光そのままをキャンバスに染み込ませる
ように丁寧にうつしとる。
自由な鑑賞を促したいという村岡佐知子は、様々にイメージを結びやすい
黒で覆った画面に色の粒をしのばせる。まぶた裏に浮き出る強い光の残像の
またたきや、宵闇に浮かぶ星屑、ネオンサインに彩られた都心の夜景など、
鑑賞者の心象風景とゆるやかにつながってゆく。
更紗やテキスタイルに登場する動植物や文様のなかから選びとったモチーフを、
陶芸の呼び継ぎのように画面上に大胆な構図と鮮やかな色彩を用い、足下の日常に
繋がる事物をとらえては物語から削ぎ取って再構築する秋山幸の絵は、
見ているうちに一幅の絵巻物を読んでいるような感覚にとらわれる。
2次元に描かれた4人それぞれの心象風景に、誘われるように呼び覚まされた
わたしたちの心象風景という層が重なった時、3次元の物語として新たな命を
吹き込まれ動き出す。
影の向こうに恐怖心むき出しで吠えたてるのか、影の向こうに
いるかもしれない仲間に呼び掛けるのか。
この不安定な世界という物語のなかで生きる術を4人に試されているのか
もしれない。
脇屋 佐起子(アートライター)
Ai Kowada Gallery
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-8-11 渋谷百貨ビル