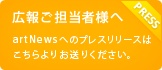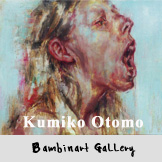垂直 Ota Fine Arts
Vertical
2012年3月21日(水)~4月 6日(金)
11:00-19:00 日・月休廊
Ota Fine Arts

モンゴルの作家であるウーリントヤの作品を見るとき、日本の我々は芥川龍之介の『蜘蛛の糸』を連想するのではないでしょうか。
蜘蛛の糸は『カラマーゾフの兄弟』に出てくるロシア民話、あるいは仏教説話から着想を得ているとも言われますが、いずれも天国と地獄という宗教的な垂直性の小説空間を持っています。 民話と説話が酷似していることに驚かざるをえません。
小林武志は古式の生け花を立てられる数少ない作家です。 日本では古くから巨木や石を円環状に配置したり倒立させたりする呪術的な風習は縄文期の遺跡に見られます。すでに平安期の文物には「石を立てる」、「石を据える」という表現がなされ、「立てる」は神への意識、「据える」は人の住むところへの感覚を表しているといわれます。
この神と生活を媒介する装置として生まれたのが「たてはな」あるいは「立花」と呼ばれる形式のいけばなであったことは納得のいくところです。 「たてはな」は中世に生まれた様式といわれますが、それ以前の奈良時代に仏への供花は行われていました。 立花が成立する平安末期には、木を立てるという自然信仰が仏への花と習合されて「たてはな」が成立したようです。
一方、現在でも大陸中国の庭には「太湖石」と呼ばれる立てられた奇石を見ることができます。「太湖石」は江蘇省の太湖に沈んでいた石灰岩が長年の浸食により穴が開いて複雑な形になったものです。 この自然の偶然性を当時の有力者は珍重したのです。
皇帝徽宗はじめ有力者は、この奇石のなかにいくつもの宇宙の存在を認め、詩を読み、瞑想し、別世界に遊んだといわれます。 別世界とは「洞天」とも呼ばれ、神仙の住処であり、これが山水の起源となるところです。雪舟はそれを理解していましたが、結果、山水画の形式のみが輸入されたのは残念なことです。今日でも中国作家が執拗に山水画を描くのは、文化大革命で悲劇的に分断された歴史と思想の連続性を獲得しようと試みる営為なのです。
山水のオリジンともいえるこの「太湖石」の宇宙観を現代に蘇らせようとするのが北京在住のジャン・ワンの彫刻です。
今回ご覧いただくのは、上記に述べた宗教的な垂直性だけではなく、蝉の孵化を人の歴史観と重ね合わせる時間軸を描く竹川宣彰の作品、抽象表現における精神性が豊かに表現された草間彌生の初期ドローイングや、ディストーション空間を描く樫木知子、風船にカメラを付けて都市を俯瞰する映像作品のグオ・イーチェンも含まれます。
Ota Fine Arts
〒106-0032 東京都港区六本木6-6-9 ピラミデビル3F
TEL:03-6447-1123