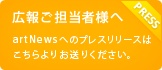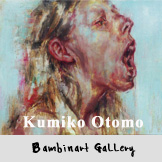越中正人 「double word」 nca|nichido contemporary art

"double word" 2008, 120x120cm C-print
前作echoesに続く、越中正人の新作double wordは、被写体に人間ではなく、植物を選んだ。
それでも意味は変わらないと、越中は言う。
表現の中心的なテーマは、つねに「集合」と「個」であり、新作のシリーズでは、「集合体を作っている個が、集合の内側にいる場合と集合の外側にいる場合の違い」に焦点を当てた。
なかでも、そこに時間の要素を導入したことが、大きな特徴になっている。
花菖蒲の集合を背景に、一輪の花(個)が枯れていく様を、連続写真として作品化したのである。
それだけならば、これらの作品は、時間の変化をともなった記録写真と捉えられるかもしれない。
確かに彼は、記録性を写真の基本的な機能として認めてはいる。
しかし、情報に還元されない、言葉では表せないものを、記録媒体としての写真に焼きつけることに心を砕いているのだ。
そこに、彼の考えるリアリティがあるからである。
とはいえ、一口でリアリティといっても、アーティストによって考え方はまちまちだろう。
越中の写真にあって、そのヒントは、自作の解説で彼が必ず引き合いに出すアイデンティティという言葉にある。
彼はアイデンティティにリアリティを感じ、それを写真に記録する。
だとすれば、彼が追求する言語化しえないアイデンティティは、「集合」と「個」の関係のどこかに隠されているのではないだろうか。
集合体のメンバーである時に感じるアイデンティティと、そこから離れて個となった時に感じるアイデンティティは同じではない。
というより、集合体の状態で、人間はアイデンティティをほとんど意識しないが、集合の外に出て個になった時、それを強く意識する。
詳しく言えば、人間は、孤立してアイデンティティを喪失しそうになると敏感になり、自分のアイデンティティの希薄化に気づいたり、それが失われる不安に包まれたりする、ということである。
アイデンティティは、それを持っている間は見向きもされないが、消えてなくなる段になって捜し求められるものなのである。
結局のところ、アイデンティティはアリバイ(不在証明)でしかない。
人間にとってアイデンティティは、永遠に不在であることを運命づけられている。追えば追うほど、それは遠ざかっていくのである。
このようにアイデンティティが不在を根本的な特性とするなら、その言語的説明が不可能であることは当然の理だろう。
ところで、新作のタイトルにあるdoubleは、どのような意味を含むのだろうか。
辞書を引けば、二倍、二重、亡霊あるいは代役という定義が出てくる。
最初集合のメンバーだった植物が、時間の経過につれ、徐々に変化(枯れる)して集合から離脱する。
集合の内側から外側への移行が起こる。
この作品は、集合の内と外で被写体が二重化される、または境界線を挟んで亡霊になる、ということなのだろうか。
いずれにせよ、われわれは、この花菖蒲のようにアイデンティティを曖昧化し、その意味の究明を先延ばししながら、時を過ごしていくのではないだろうか。
と、ここまで書き進めてきて、言葉での説明に翻弄されてきたことに気づいた。そして、あらためて越中の新作に視線を注いだ。
枯れていく花の、なんと艶かしいことか。
対象をクローズアップして得られた、予想外の効果ではない。衰えつつある個が見せる一瞬の生の輝き。
これが、未来に死が待ち受ける有限なものに、現在が解き放つエロスの濃密な匂いをまといつかせているのである。
市原研太郎 (美術評論家)
nca| nichido contemporary art
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-3-3
ダヴィンチ京橋B1