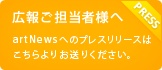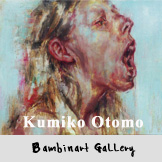森田浩彰 「Clockwise」 青山|目黒
オープニングパーティー:5月31日(土) 19:00から

日常とアートの円環をめぐって
竹久 侑 (水戸芸術館現代美術センター 学芸員)
日用品による日常風景での物語の創出―これが、森田浩彰の2000年代初期の作品群に共通する特徴といえるだろうか。
筆者がはじめて見た森田の作品は《From Evian toVolvic》[2001]。壁の上にエヴィアン、下にヴォルヴィックが置かれ、エヴィアンに開けられた小さな穴から水がこぼれ落ちヴォルヴィックのボトルに回収された形跡を見せる軽妙なインスタレーションだ。
水が商品間を移動したという物語が読みとられた瞬間、本作のシニカルな社会批判が浮かびあがる。
ミネラル.ウォーターという自然資源を商品化して売るという経済至上主義的な思考、そしてラベルがなければ中身の判別が困難で消費者はコンテンツより付加されたイメージをもとに購買するという過剰な消費社会の有り様を、本作はユーモラスに揶揄してみせた。
また、作品の素材に天然資源のなかでも政治性を孕む石油などでなく、いたって身近で日常的な水が選ばれたことは、以降の作品にも共通する、森田の日常性への関心を端的に示していた。
2つの使い捨てカップがごみ箱のなかで扇風機の風を受けて舞うインスタレーション《Two Cups in Dustbin》[2001]では、扇風機という日用品の簡単な仕掛けによって、ひどくチープでありふれたモノがとたんに有機性を帯び、まるで子猫がじゃれあっているかのような愛らしく生々しいイメージを連想させる。
また《Screws》[2002]では、壁から突き出た2本の曲がったネジがゆっくりと大きな円を描くように回転する。ネジがぶつかりそうでぶつからないスレスレの緊張感は、ワルツを踊りながら互いの気持ちを探りあう男女の姿を呼び起こす。
このほかにも森田の初期作品には、鏡、トイレットペーパーなどのありふれたモノになんらかのシンプルな仕掛けを加えることで、センチメンタリズムやユーモアを醸成するものが多く見られる。
なかでも上記2作にうかがえる、日用品の感傷的な擬人化、日常におけるポエジーの創出は、フェリックス・ゴンザレス・トレス(1957-1996)の《Untitled (Perfect Lovers)》[1991]やガブリエル・オロスコ(1962-)の初期作品《Crazy Tourist》[1991] および《Breath on Piano》[1993]に通ずる。
この連想は、森田が2004年に《オロスコはボイスをみ、ボイスはデュシャンをみ、デュシャンはあなたをみる》でオロスコに言及したことをふまえるとあながち間違いではないだろう。
森田の2000年代初期の作品群は、デュシャンが創始した、大量生産品のアートへの転化、つまり価値の転換という王道のコンセプチュアル・アートの系譜を、オロスコらを経て森田自らが引き継いでいるこ
とを顕示する。
だが、デュシャン以降さまざまな美術家がすでに多角的に扱ってきた日常のアートへの転用について、森田は自らの独自性を模索しているように見えた。
そして2004年ごろから森田は時間という概念を扱いはじめた。
時間を表象する「時計」を自ら作るという行為をとおして、時間という抽象観念の探究にくりだした。これを機に森田の作品は、従来の感性に導かれたような軽妙さが薄まり、日常という領域の探索に思考の深みをのぞかせるようになる。
その好例である《Clockwise》[2008]で、森田は自分のアトリエにあった工具で時計をつくった。といっても、本作のなかで工具は、日常の道具(=モノ)から表象に転換されている。
00:00から23:59までの1440通りの数字の組み合わせを工具をさまざまに並べ替えることで表現し、時を進ませるごとに撮影した。
その映像素材を実際の時間尺に合うようつなぎあわせ、24時間を表す時計を映像作品としてつくりあげたのだ。
森田は本作を仕上げるために、この気の遠くなるような作業を3年間断続的に繰り返した。
このように時間という概念の追究が自らの精神力との対峙と並行した前例に、ローマン・オパルカや河原温が挙げられる。
だが森田の見据える先は、偉大な先人らとは異なる。森田は、自戒的ともいえる行為をとおして時間
を非世俗的な立ち位置から扱うことを求めていない。なぜなら、森田にとって時間は、哲学的テーゼである以前に、食事や睡眠といった日々の行為を自ら営み、他者と共有するための「指標」であるからだ。
それだけでない。楽しい時間は速く過ぎ、そうでない時間は遅く過ぎると感じるように、何にもゆるがされない基準であるはずの時間は、日々の営みにおいてひとの心が浮き沈みするのに連動し、絶対性が希薄になりあいまいになる。
森田の考察の対象は、まさにこのような日常のなかで体感される時間の相対性だ。
《Clockwise》は、映像という時間軸上に成り立つメディアの特異性をいかして、鑑賞者に時間を身体的に感じさせる。
時の進行に即したメディアであるために、鑑賞者は本作を見るにあたって、その表象するところの時間について「思考」するよりもまず先に、否応なしに時間を「体感」することになる。
そして、《Clockwise》を見てつまらないと思えば1分も経たないうちに、つまり表象としての工具が時を刻む展開を見ないままに立ち去るかもしれないし、逆に興味を覚えれば工具の組み合わせの妙が示す時の刻みに見入るだろう。
つまり《Clockwise》は、鑑賞者の本作に対する興味の程度を、それが作品中に表象する時間の長短によって実測することになる。
さらにいってしまえば、本作はひとが内部にしまっておけたはずの心情を、時間という尺度で鏡に映しだすようにあらわにするのだ。
もっとも、24時間の時計をつくるのに3年をかけた森田こそ、その日その日の自己の集中力や気分の高低を、自らが作品中に刻む時間尺の長短によってまざまざと知らしめられたはずだ。
このように森田は、映像というタイムベース・メディアの作品を鑑賞もしくは制作するという、日常的とは言い切れない行為をとおして、平常に偏在する時間を特別な視点から意識させ、時間の(尺度としての)絶対性と(身体感覚上の)相対性を同時に顕在化する。
それが森田が《Clockwise》で試みた挑戦だ。
秋に向けた次作の構想を森田に聞いた―実際のさまざまな日常風景のなかで手動で時を刻みゆくパフォーマンスをとおし、時間の長短が状況や感覚によって多様に感じられることを可視化する映像作品が企図されている。
これによって《Clockwise》で扱った「感覚上の時間の相対性」という解しにくいアイデアを日常という見慣れたフレームに落とし込み、身近な方向へと展開させることになるだろう。
となれば森田は次作で、2000年代初期に披露した日常における物語づくりの軽妙でユーモアな視点を、それ以降の深淵な観念の探究に織り交ぜることになるのではないか。
次作をもってこのふたつの世界観が掛け合わされることを筆者は予感し、森田浩彰が次なる段階へと飛翔する期待を胸に募らせている。
青山|目黒
東京都目黒区上目黒2-30-6
TEL: 03-3711-4099
http://www.aoyamahideki.com/